
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科教授

![]()
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科教授
![]()

![]()
1603年に彦根山に城を構築と決定する。1604年より普請を開始し、1622年には現在の姿となった。現在との違いは
大手御門が正式な門であった事で、あくまで表門は大阪を向いて「にらみ」をきかしていた。大手門から天平櫓へ通じる
道が正式で、現在も残されている。
 |
城郭の違い 時代の変化 城郭の特徴 築城の期間 彦根城の 特に時代の変化 城郭の防御の特徴 石組の年代考証 中井先生の案内により表御門(二の丸)より授業開始 |
|
| 創建当時の石組で年代的には最も古い城郭 (天平櫓の裏側) |
![]()
![]()
![]()



二段構えの石垣で石垣崩れを防止する有効な手段とされる。 表御門から彦根城博物館の前付近の切岸
内堀の彦根城は人工的に岩盤を削り取り、登ることの出来ない壁を作る。彦根城内は山切岸と呼ばれる
箇所が全周にわたり作られ、敵の侵入を防御している。
![]()


攻めて来る敵を上下移動により侵入を防ぎ、山城の竪堀と同じ働きをする。彦根城にも5か所程度ある。
![]()
![]()



彦根城の大堀切と言われ、右の天稟櫓より、左上部からも鉄砲・矢の攻撃を受ける。
何気なく通り過ぎるが大規模な堀切、天平櫓までは屈折の連続でどの場所からも攻撃を受ける。


天秤櫓で橋は廊下橋といわれ、取り壊しが可能で天秤櫓より攻撃する。
![]()
![]()



中井先生によれば天秤櫓の石垣は右・中央・左では石組の年代が違うとの事。よく見ると違いがわかる。
真ん中の写真は矢穴により、石材を切断した跡で、中井先生は安土城ではなく、彦根城では見かける。
![]()
![]()



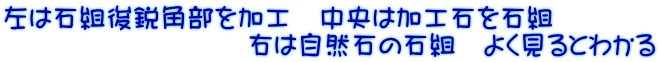

廊下橋で天秤櫓の説明をする中井先生と生徒


天秤櫓から天主へ続く城郭 天秤櫓内で説明を聞く生徒
![]()
![]()



天主の矢狭間 天主 天主鉄砲狭間
![]()
![]()
天主から三重櫓へは裏側と思われるが、大堀切があり屈折した石垣に囲まれ、天主も高い城壁の上にあり
こちらから見る天主の方が素晴らしい。また、中井先生によれば創建当時の石組が多く残っている場所であるとの事。



創建当時の石組と登石垣みたい ここにも門構え 三重櫓側からみる高い城壁の天主



石組に組み込まれた石塔 進むと前・右・左上部より攻撃を受ける ここにも門構え。説明する中井先生
![]()


創建当時のままで、天秤櫓同様守りの「かなめ」 彦根城では珍しい竪堀
![]()


三重櫓の城壁の横は大堀切 ここにも大堀切で防御している



三重櫓も大堀切の上には橋がかかる 創建当時の城郭が多く残る
![]()



創建当時は正門で大阪方向を向き「にらみ」をきかす。 門構えの礎石も残るが、現在はひっそりとしている。
![]()
| 普段観光客が少ない三重櫓から の天主の姿。 ここから見る天主は高い城壁の 上に天主が建ち、入母屋破風、 唐破風、切妻破風、飾り高欄付き 廻縁など外観の美しい姿が見ら る。 ここからみる天主は必見!! 一度は 行ってみたい場所 |
 |
この天主も移築で内部には使わないほぞ穴が残った 木材があり、移築と分かる。 内部には装飾はなく、防御のみの鉄砲狭間・矢狭間・ 隠し部屋などがあった。 中井先生によれば、城主は天主に生涯の内に一度くらい しか訪れない場所であり、平和な時代は天主の必要性が なかったとの事。 彦根城築城以来戦火になる事無く、明治時代をむかえる。 中井先生によれば、大阪夏の陣・冬の陣が終わった後の 時代に正門が大手御門より現在の表御門に変更された との事。 |
![]()



びわ湖側の景色 中央部の低い山は磯山 中央部の山は佐和山城跡

一人足りませんが天平櫓・廊下橋にて中井先生と生徒
![]()
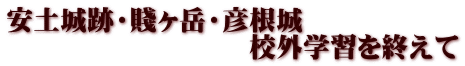
それぞれの特徴があり、それまでの城郭方法が土による土塁・堀切・竪堀・犬走りなど自然の地形を利用した
方法であった。織田信長は石組による城郭を作り、立体的とした防御を構築。私的ではあるが近くの観音城を
参考にしたのではないか。
観音寺城は六角氏が支配していたが、浅井長政に敗れ、織田信長にも敗れ廃城となったが、現在も石組による
城郭が残っている。
当時の観音寺城は石組の城郭であったが、防御には弱かったとある。
![]()
観音寺城から安土城までは直線距離は3km.未満と非常に近く、織田信長は防御に優れて壮観な城を構築した。
織田信長は天主を居住空間とし、従来の守りの天主から華麗な五重七階・金箔瓦葺の城を構築した。
![]()
賤ヶ岳砦は柴田勝家の近江進行を防ぐ目的で余呉湖を中心に、北部には柴田勝家軍、南部には豊臣秀吉軍が
自然の地形を利用した砦を作った。短期間で砦を作る必要があったので、地形を利用した堀切・竪堀・土塁・切岸
犬走りなど簡易なものであった。
![]()
彦根城は年代的にも1600年以降の城であり、防御は自然地形を生かし、城郭を作りあげた城と言える。
堅固な城郭を構築し、二重三重の防御がされたが平和な時代には不要であった。
今までは何の気もなく幾つかの城をみてきたが、今回の校外学習で観察する視点が大きく変化し、先人の知恵を
改めて知ることになった。
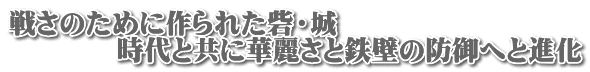
![]()
![]()